 2009年9月〜2010年4月
2009年9月〜2010年4月  戻る
戻る
4月9日
相変わらずの寒さで成育がかなり遅れている。エンドウはようやく蔓が延びてきてネットに絡み始めた。タマネギのマルチは強風のためはがれること5度目、度重なる修復にも耐えなんとか残っているが、茎は途中で折れ葉は飛び散りで散々である。今年の収穫は期待しない方が良さそう。去年の秋に蒔いて冬を越し成長するはずであったキヌサヤエンドウはすっかり枯れてしまっていたのは4月上旬に分かっていたため、急遽バックアップ用にスナックエンドウを種まきしたが、その芽は出始めたので期待しよう。



スナックエンドウ エンドウ タマネギ
3月19日

 タマネギも順調に成長しているが、風が強かったのかマルチが完全に外れてしまっていた。再度張りなおして固定したが毎年発生する事件でどうしようもない。
タマネギも順調に成長しているが、風が強かったのかマルチが完全に外れてしまっていた。再度張りなおして固定したが毎年発生する事件でどうしようもない。
エンドウは春が来て成長を加速しているようで、先週のネットが少し役立つときが来ている。
3月12日
エンドウも寒さをなんとか乗り越えてそろそろネットを張る必要が出てきたので、支柱を立てネットを両側から張った。ネットは1.8m×32mで100円ショップから購入
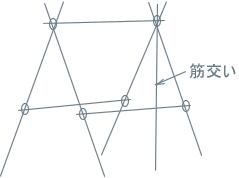
2月26日

エンドウとタマネギは寒い冬をなんとか越えて成長を始めた。
もう少し暖かくなるとエンドウに支柱を立てネットを張る作業が必要。
2月19日
葉もの野菜の収穫は順調でホウレンソウなど新しく種まきしたものもあるが、そろそろ夏野菜の準備で3月末をめどにして片付けられるようにしないといけないかもと思っている。エンドウの不織布カバーは相変わらず風により飛ばされているためあまり役に立っていないかも知れない。ひょっとして気休めかな?
夏野菜(ナス、ピーマン、シシトウ、トウガラシ、パプリカ)の種まきをした。今年は楽園サークル独自のパプリカも新しい試みとして種まきした。
2月12日
2010年夏野菜の種類と配置を検討した。3年めともなると連作障害を考慮するのに苦労した。結果は2010年夏野菜のページに
2月5日
先月から作業はほとんど温室内での葉もの野菜、収穫と草取り、それに新しく種まきと同じ内容で終わる。外は寒さが厳しくキヌサヤエンドウが頑張っているが少し枯れ始めたものも現れてきたので霜よけの意味で不織布でトンネルを作った。
今年の春夏野菜の内容を決めるため各人が種類と場所の検討に入った。来週には全員の検討結果が出揃うので集まって決める予定。
連作障害を発生させないため間隔をあける野菜類
1年はあける ソラマメ、レタス、キャベツ、かぶ
2年はあける ホウレンソウ、白菜、ジャガイモ、ネギ
3年はあける インゲン、トマト、キュウリ、ピーマン、サトイモ
4年はあける エンドウ、スイカ、ナス
連作障害の無い野菜 大根、人参、小松菜、サツマイモ、カボチャ
1月25日
今日は温室内で収穫と整理が主な仕事。開いている畝に夏野菜を植えるまで2ヶ月ぐらいで収穫できるように最後の葉もの野菜の種を蒔いた。タマネギのマルチが冬の強い風のため、ひらひらと空中を舞っている。土を被せても雨が少なく土が粉状になり、更に霜柱で浮き上がってしまう。こんどはしっかりと土を被せて足で踏みつけておいたがどれだけ持ってくれるか。温室内にはサツマイモを土中に埋め、ひょっとして芽が出れば儲けものと言うくらいのつもりで試してみた。2ヵ月後には立派な苗が出るように・・・・
1月22日
冬真っ盛りの日、気温も3日ほど前は4月並まで上がったが今日は平年並みの寒さであった。温室内の葉もの野菜が収穫時期に来ているので間引きながらの収穫をした。どれも2週間後には大きくなって食べごろになりそう。





ホウレンソウ カブ 小松菜 水菜 春菊



タマネギ エンドウ 夏野菜作付け場所 手前:タマネギ 左:エンドウ
夏野菜用の場所は耕されしばらく休眠して、5月ごろには種まきから苗の定植になる。どのような野菜をどこに植えるか現在検討中。
1月15日
昨日から寒波が来て毎朝霜柱が出来ている。昨日の強風のためタマネギのマルチがはがされ風に舞っていたので土寄せして再度固定した。温室外の畑はすっかり耕され綺麗になっていた。後は春野菜のジャガイモを初めとして夏野菜の準備に入ることが出来る。温室内では小松菜は収穫でき、水菜は間引いたのも十分食べれるまで成長している。先週片付けたブロッコリーの後にホウレンソウの種まきをするため苦土石灰と化成肥料を蒔いて耕し畝を作って十分な水撒きをしておいた。来週来るときはホウレンソウの種を一晩水に漬けておき、この畝に種まきをする。もう一つの畝には苦土石灰と化成肥料を蒔いた後、1ヶ月の時間差で収穫できるのを期待して株と水菜の種を蒔いた。
1月8日
新年初めての作業日。今年は冬晴れが続き天候に恵まれている。大根は全て収穫されており、残っているブロッコリーと春菊も今日の収穫で最後となって撤去することにした。ブロッコリーは脇芽が少し大きくなっており食べれるぐらいになっているものが結構な量になっている。残念ながら春菊は収穫できるものは無くそのまま廃棄となった。葉もの野菜のうち小松菜は収穫時期に入っているので大きなものから収穫を始めた。ホウレンソウ、水菜、株はまだ少し時間がかかりそう。1月下旬頃までには全て収穫でき温室も綺麗に片付くものと思われる。
12月18日
今年最後の作業はハクサイとキャベツの最終収穫と撤去、ブロッコリーと大根の収穫を行った。ハクサイは全部で20個ぐらい、キャベツは残念ながらほとんど割れており、更に根元が腐って(菌核病)いて中心部分ぐらいしか食べれそうになく、それも10個ぐらいと散々な出来栄え。昨年も同じような経験をしたが今年も同じであった。来年はキャベツ対策をしないと収穫時期が1週間ぐらいになってしまう。大根も食べきれないので種まきも少なめにすることを考える。
温室内の葉もの野菜はもう少し生長に時間を要する。年末か新年早々が適当かも? ブロッコリーは脇芽がたくさん付いているので温室内の高温で育ってくれることを期待して残しておいた。
キャベツの菌核病は結球期頃から発生しはじめ、比較的低温の気温20℃前後で曇雨天が続く時に多く発生することが知られている。初めは下葉の葉柄の付け根近くに水浸状の病斑ができ、次第に病斑が茎・葉柄を伝わって結球部にまで進展し、腐敗を起こす。症状が軟腐病による腐敗に似ているが悪臭はなく、罹病した結球葉をはがしてみると、内部に白色綿毛状の菌糸と黒い大型の菌核を見つけることができる。この菌核は土壌中で4〜6年間は生存でき、次年度以降の伝染源になる。本病を防除するためにはイネ科作物との輪作を行う、発病株をできるだけ早く抜き取る、深耕して菌核を土中深く埋め込むなどの耕種的管理を行うとともに、発病前からの予防的な薬剤散布を行うことが大切。シンジェンタからは、フルジオキソニル剤のセイビアーフロアブル20の1,000倍液散布が登録されており、また、本年6月にはアゾキシストロビン剤のアミスター20フロアブルの2,000倍液散布が新たな防除剤として登録になった
12月4日
12月に入り冬野菜も収穫最盛期と言うより、すでに遅すぎかもしれない。キャベツは中心付近で大きく割れるし、ブロッコリーに花も咲き、白菜は根元が腐ってきた。更に大根は太くなりすぎ芯の部分が腐り始めている。冬野菜は一度に収穫しなければならないが、とても食べきれるものではない。





一番実を取った後脇芽から出た実とすでに花が咲いたブロッコリー 太りすぎた大根 中央部分に割れ目の入ったキャベツ 菌核病
キャベツが結球するとき外側の葉から始まるので、それが出来上がった後で内側の葉が成長すると外側の葉が小さすぎて割れてしまう。従って収穫時期は大きさで判断するのではなく、中にどれだけ詰まっているかつまり硬さで選ぶべきということ。そこで割れるのを少なくするためには種まき時期から時間差を作って植えないと駄目と言うことがわかる。
もう一つの方法としてキャベツは外側の下葉で作られた栄養が、中心に集まるため中心の葉が成長しすぎて割れると言うことになるので、球が大きくなった頃に下葉を取ってしまうと割れにくくなる。
温室内に蒔いた野菜は順調に芽が出て育ってきているが、これも一度に収穫時期が来るので時差を作って種まきをする計画にしなければいけない。



カブ ホウレンソウ 小松菜


外に植えたタマネギは種から育てた苗と購入した苗では大きさがかなり違って、育苗の大切さが定植後の生育に大きな影響をすることが改めて実感している。
右の写真で手前が購入した苗、奥側が種まきして育てた苗
しかしエンドウはしっかりと発芽し、順調に育っているので来年の春にはたくさんの豆を収穫できそう。
11月27日
白菜、キャベツは最適時期。この日を過ぎるとキャベツは割れるし、白菜は根元から腐ってくる。本当に収穫時期は一度にやってきてどうしようもない。ブロッコリーは第1果を収穫後脇芽を残しておくと再度実が付いてきそう。カリフラワーは第1果で最後だからこの手は使えない。
11月13日
冬野菜の収穫最盛期、白菜、大根、キャベツはすっかり大きくなり食べごろになった。しかし成長はすべて同じ時期になるため食べるのは大変。どうにかして時期を部分的に遅らせる方法が無いものかを考えてしまう。温室内ではトマトが最終になり今日は赤くなっていないものを含めてすべてを収穫して撤去した。蒼いものは1週間ぐらい室内に放置しておくと赤くなるかもしれない。ブロッコリーとカリフラワーも収穫できるようになってこれから毎週20個ぐらい取れそう。2週間前に定植したタマネギはかなりの数が育たないで枯れてしまった。止む無くホームセンターで苗を買ってきて枯れた部分に追加で定植した。またトマトやホウレンソウを撤去した畝に苦土石灰と化成肥料を蒔いて、葉もの野菜(春菊、水菜、小松菜、かぶ)を種まきした。
11月6日
冬野菜のスナックエンドウとキヌサヤを40cm間隔で千鳥に2粒づつ種まきした。
右の写真で右側がタマネギ、左側がエンドウとキヌサヤの畝。順調に発芽すれば小さな苗の状態で冬を越し、春になると急に成長して5月ごろ実をつける。
収穫はキャベツ、カリフラワー、春菊、トマト、ホウレンソウと今日もたくさんであった。モロヘイヤはこれ以上収穫が望めないので撤去した。ホウレンソウも少しだけ残してほとんど収穫。その跡地に小松菜を種まきしてみた。カリフラワーも大きなものが少しあったので1株だけ試しに収穫してみた。大きな株にしては実が小さく効率の悪い野菜である。
キャベツと大根も収穫できるまで大きくなっていたので一つづつ収穫



カリフラワー 白菜 キャベツ
10月30日
今週は畝にマルチを張ってタマネギを20cm間隔で3列に定植した。種から蒔いた苗は育ちが悪く時期的には少し早いようだが決行した。タマネギ用にもう1列畝を作りマルチを張ったが、苗が足りなくなり追加で購入することにした。

収穫した野菜はトマトにホウレンソウ。
大根を試しに1本抜いてみたが結構大きくなっており十分美味しく食べれそう。
温室内の空いた場所には小松菜の種を蒔いておいた。
ブロッコリやカリフラワーはまだ実が見えない。
10月23日
先週は落花生、サツマイモ、トマト、春菊、モロヘイヤ、小松菜と多くの野菜を収穫したので、収穫できなかったサトイモを収穫した。2種類のサトイモで親芋の食べれるセレベスと食べれない土垂(どだれ)がある。セレベスはインドネシア原産で赤味があってホクホクとして美味しい。


土垂 セレベス
 落花生は先週土から引き抜いて裏返して干していたの豆を茎から引き離す作業は結構面倒で時間がたっぷりかかってしまった。白菜やキャベツは虫も付かず結構順調な生育。このまま行けば11月下旬に収穫できそう。
落花生は先週土から引き抜いて裏返して干していたの豆を茎から引き離す作業は結構面倒で時間がたっぷりかかってしまった。白菜やキャベツは虫も付かず結構順調な生育。このまま行けば11月下旬に収穫できそう。


落花生収穫風景 ブロッコリー ホウレンソウ



白菜 キャベツ タマネギ
10月16日
トマトはオンシツコナシラミの害虫がかなり発生していて、同じ温室内の他の野菜にも影響するかもしれないので消毒をする。モロヘイヤや春菊、トマトを消毒より先に収穫できたが、以後1週間は収穫できない。
タマネギは移植後3割ぐらいが枯れてしまったので、11月の定植時にはかなり不足するかもしれない
 ブロッコリーとカリフラワーは順調に育っていて、まだ区別が付かないけれど実が付き始めるのはいつ頃だろう。キャベツに白菜は少し巻き始める気配が見える。成長しだすと早いもので来月下旬には収穫できる予定。
ブロッコリーとカリフラワーは順調に育っていて、まだ区別が付かないけれど実が付き始めるのはいつ頃だろう。キャベツに白菜は少し巻き始める気配が見える。成長しだすと早いもので来月下旬には収穫できる予定。






大根 白菜 ホウレンソウ 小松菜 モロヘイヤ
10月7日
今年初めて上陸しそうな台風がやってきた。温室は今まで周囲のビニールを上に上げて通風を良くしていたが、台風が近づいているので飛ばされないようにすべて下ろしてきた。今週は雨が続いているので水撒きもしていなかったが、移植したタマネギもなんとか根付いたようで軽く水撒きをしておいた。ホウレンソウやブロッコリー、セロリなどは順調に育っている。
10月2日
今日はあいにくの雨、と言っても久しぶりの雨らしい量が降った。水不足の野菜たちには待っていた水である。キャベツや白菜、大根などはびっくりするほど大きくなっていてこのまま順調に行けば、少しはやめの収穫時期が来そうだ。トマトには相変わらずコナシラミが集まっているため、消毒の変わりに接着剤を塗った紙をぶら下げるとそれに集まってきて捕まえることが出来る。トマトの花と同じ黄色い色に引き寄せられるらしい。トマトは割れたり落ちてしまうこともあるので、少し赤みのかかった状態でも収穫しないと2日空ける熟しすぎになってしまう。タマネギは双葉まで成長していたので温室内の一部を整理してそこに移植した。約1ヵ月後には本来の畑に定植できるよう成長するのを待つ。




温室内のブロッコリー ホウレンソウ 収穫したモロヘイヤ とホウレンソウ 移植したタマネギの苗



トマト 春菊 温室コナシラミを捕まえる接着紙
9月25日
夏野菜のナス、ピーマン、シシトウ、トマトのすべてを撤去して後片付けをした。さすがにナスは収穫できても食べれないものばかりであったが、ピーマン、シシトウはまだまだ収穫できそうでも止む無く終わりにした。温室内のトマトはかなり温室コナシラミニやられているので収穫も思ったほど取れなかった。そのほかのブロッコリーやカリフラワーは順調に育っているが、やはり害虫のため消毒をした。落花生、サツマイモ、サトイモは10月中旬から下旬に収穫時期を迎えそう。タマネギの苗も先端に種の殻をつけた状態まで育っているので来週には移植して定植する11月ごろまでに大きく育てる必要がある。
9月18日
台風が近づいているためキャベツに白菜、ブロッコリーの土寄せをした。先週定植したこれら3種類は無事根付いて育ち始めた。台風の風で根元が揺さぶられると折れてしまうかもしれないので土寄せをして根元を固定する。温室内ではトマトにオンシツシラミがまた発生しており、厄介者が出てしまったが収穫中なので消毒できずに様子見となる。先週収穫してから1週間経つが赤くなっているのは少なく、しばらく時間がかかりそう。ホウレンソウは無事発芽して順調に育っている。タマネギは発芽していたが根の上向いて伸びている苗もあって苗そのものが浮き上がっているので、上から細かい土をかけ根を土の中に入るようにして散水した。



ブロッコリー 春菊 白菜



ホウレンソウ キャベツ 発芽したタマネギ
 9月16日
9月16日
大根の間引きと追い肥(1畝当り800g)をして土寄せをする。
ホウレンソウの畝に苦土石灰をばら撒いたあとで、散水をしてPH度を調整する。
9月11日
トマトが色付き始めてそろそろ収穫できそう。今日は約30個ほど収穫できた。このトマトは何故か皮に切れ目が入ってしまうので丁寧に収穫しないと割れたトマトばかりになりそう。また伸びてくる先端をとめることで実の付くのは5段目まで、そこから先は熟すのみ。温室内ではモロヘイヤも収穫でき、取り方は上から3〜4枚のところを茎ごと切り取る。そのまま10日ぐらい経つとその周辺から新しい葉が育ってきて又収穫できることを繰り返す。先週蒔いた大根はしっかりと発芽していたし、定植したブロッコリーとカリフラワーはネキリムシの被害も無く育っている。
又新しく蒔いたのはホウレンソウ、小松菜、タマネギ、定植したのは白菜、これで冬野菜の前半は終了した。これから夏野菜のサツマイモ、落花生、サトイモを収穫したあとタマネギを定植すると冬野菜は完了することになる。




赤くなってきたトマト ブロッコリー モロヘイヤ 大根
9月4日
冬野菜の種まきと定植が最盛期。ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、大根をそれぞれ行った。モロヘイヤと春菊はそろそろ収穫時期。





ブロッコリー カリフラワーとキャベツ 大根 モロヘイヤ 春菊
8月28日
トマトに温室コジラミが発生してきたので消毒。セロリの苗を50cm間隔で千鳥に定植。ブロッコリーの双葉苗をポットに移植。それぞれ作業をしたが、暑い日の温室作業のため結構暑かった。ナスやピーマンシシトウなど夏野菜もそろそろ終わりに近づき収穫も少なめであった。サツマイモ、サトイモ、落花生はまだしばらく時間がかかるため冬野菜のキャベツ、白菜、大根を植える場所に苦労する。
8月23日
温室に定植したカリフラワーとブロッコリー、ポットに移植した苗は根付いているか心配であったので水撒きをするために様子を見てきた。枯れることも無く無事根付いているようでしばらくは水彼をしないように頑張る必要がありそう




定植したブロッコリー カリフラワー 間引きしたブロッコリー 移植したカリフラワー
8月21日
種まきしてから2週間カリフラワーとブロッコリも双葉から本葉に移ってきている。しかし不思議なことが起こった種まきしたから違った環境の4箇所で育てた苗は育ち方が大きく違っていた。最大は約10cm、最小は約3cmの長さとなっている。種まき後の時間はまったく同じで、違うのは温度と日照時間だけ。これでこのような差が生じるのはなぜだろうか。



ブロッコリー 小さなカリフラワー(左)とブロッコリー(右) カリフラワー
長く成長した苗の一部は直接畑に植え、残りはポットに移植して育てることにした。
葉もの野菜は順調に育っている。トマトも実が大きくなってきている。




小松菜 モロヘイヤ 春菊 トマト
8月14日
温室内の野菜はホウレンソウを除いてしっかり生長している。トマト(りんか409)も第3段目ぐらいの花も咲き始め、1段目の実が大きくなって今年は収穫が楽しみになってきた。このまま発病しなければいいのだが? キャベツも双葉から本葉が出かかっている




小松菜 モロヘイヤ 春菊 キャベツ
8月7日
温室内に種まきしたホウレンソウ、モロヘイヤ、小松菜、春菊は発芽し始めていた。トマトは脇芽を取り2段目の花にトマトトーンをかける。





ブロッコリーとカリフラワーの種まきをして、それぞれ自宅に持ち帰り育てることに。成長したらポットに移植した後更に育成して畑に定植する。
8月11日
発芽し始めたブロッコリーとカリフラワー。カリフラワーのほうが成長早く約7cmの背丈
8月3日
トマトの第1花が咲きそろったのでトマトトーンをかける。脇芽も順調に取除き、伸びてきた本枝を固定した。最近は夏と言っても低温ですべての野菜は成長が遅れている。種まきした小松菜は芽が出始めたがこちらは種まき時期を少し早い目にしたため、気温が高すぎて成長が狂ってくるかも?
7月31日
温室内にモロヘイヤ、小松菜、ホウレンソウ、春菊を筋蒔きした。ホウレンソウは事前に苦土石灰をバケツ4分の一程蒔き耕した後に種まきをした。なおブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、白菜、タマネギは種まきをポットに行って育苗をしてから定植するが、タマネギだけは種まき後各自が分担して持ち帰り、家で水撒きをして育てた後に学校に持ち込み定植することにした。
7月24日
 トマトの大玉苗を温室の北側一列に定植して支柱を立て固定した。昨年は途中で疫病が発生してほぼ全滅してしまったので今年は定期的に消毒をして収穫まで頑張る。トマトは脇芽取からトマトトーンによる受粉と結構忙しいので管理が大変である。温室内はこのほかにセロリや小松菜、春菊、ホウレンソウ、カブなど葉もの野菜を栽培する予定。
トマトの大玉苗を温室の北側一列に定植して支柱を立て固定した。昨年は途中で疫病が発生してほぼ全滅してしまったので今年は定期的に消毒をして収穫まで頑張る。トマトは脇芽取からトマトトーンによる受粉と結構忙しいので管理が大変である。温室内はこのほかにセロリや小松菜、春菊、ホウレンソウ、カブなど葉もの野菜を栽培する予定。
7月27日
温室内のため雨が降っても濡れないため土は乾きっている。水撒きをしてトマトの萎えるのを防ぐ。また花も咲き始めたのでトマトトーンの準備をする。
今年の作付け計画は次の通り
| 夏 野 菜 |
 |
冬 野 菜 |
| スイカ |
カボチャ |
ブロッコリー・カリフラワー |
| 落花生 |
キャベツ(9月上旬)2列 |
| ナス |
ピーマン |
シシトウ |
ミニトマト |
ジャガイモ(3月上旬) |
| トウモロコシ |
白菜(9月中旬) |
| サツマイモ |
タマネギ(11月上旬) |
キヌサヤ |
エンドウ |
| サトイモ |
タマネギ(11月上旬) |
| トウモロコシ |
|
青首大根(9月上旬)2列 |
| 温室 |
トマト(7月中旬) |
| セロリ |
ブロッコリー(9月上旬) |
| 小松菜(7月末) |
カリフラワー(8月下旬) |
ホウレンソウ(7月末) |
ホウレンソウ(10月上旬) |
| モロヘイヤ(7月末) |
ブロッコリー(9月上旬) |
春菊(7月末) |
カリフラワー(8月下旬) |
| 種類 |
播種・種まき |
1畝当り列数 |
植付け長さと苗株間隔 |
苗数 |
種or苗 |
| タマネギ |
11月上旬 |
畝幅80cm 25cm間隔4条 |
25mに25cm間隔 |
25m÷0.25m×4=400本 |
苗 |
| 白菜 |
9月中旬 |
畝幅50cm 1条 |
25mに50cm間隔 |
25m÷0.5m=50本 |
苗 |
| キャベツ・ブロッコリー |
8月下旬 |
畝幅50cm 1条 |
25mに50cm間隔 |
25m÷0.5m=50本 |
苗 |
| 大根 |
9月上旬 |
畝幅50cm 1条 |
25mに40cm間隔 |
25m÷0.4m×5粒=315粒 |
種 |
| トマト |
7月中旬 |
畝幅50cm 1条 |
25mに0.4m間隔 |
25m÷0.4m=60本 |
苗 |
 戻る
戻る



 タマネギも順調に成長しているが、風が強かったのかマルチが完全に外れてしまっていた。再度張りなおして固定したが毎年発生する事件でどうしようもない。
タマネギも順調に成長しているが、風が強かったのかマルチが完全に外れてしまっていた。再度張りなおして固定したが毎年発生する事件でどうしようもない。
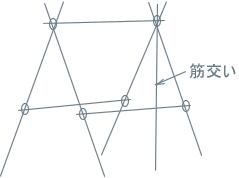





























 落花生は先週土から引き抜いて裏返して干していたの豆を茎から引き離す作業は結構面倒で時間がたっぷりかかってしまった。白菜やキャベツは虫も付かず結構順調な生育。このまま行けば11月下旬に収穫できそう。
落花生は先週土から引き抜いて裏返して干していたの豆を茎から引き離す作業は結構面倒で時間がたっぷりかかってしまった。白菜やキャベツは虫も付かず結構順調な生育。このまま行けば11月下旬に収穫できそう。





 ブロッコリーとカリフラワーは順調に育っていて、まだ区別が付かないけれど実が付き始めるのはいつ頃だろう。キャベツに白菜は少し巻き始める気配が見える。成長しだすと早いもので来月下旬には収穫できる予定。
ブロッコリーとカリフラワーは順調に育っていて、まだ区別が付かないけれど実が付き始めるのはいつ頃だろう。キャベツに白菜は少し巻き始める気配が見える。成長しだすと早いもので来月下旬には収穫できる予定。


















 9月16日
9月16日































 トマトの大玉苗を温室の北側一列に定植して支柱を立て固定した。昨年は途中で疫病が発生してほぼ全滅してしまったので今年は定期的に消毒をして収穫まで頑張る。トマトは脇芽取からトマトトーンによる受粉と結構忙しいので管理が大変である。温室内はこのほかにセロリや小松菜、春菊、ホウレンソウ、カブなど葉もの野菜を栽培する予定。
トマトの大玉苗を温室の北側一列に定植して支柱を立て固定した。昨年は途中で疫病が発生してほぼ全滅してしまったので今年は定期的に消毒をして収穫まで頑張る。トマトは脇芽取からトマトトーンによる受粉と結構忙しいので管理が大変である。温室内はこのほかにセロリや小松菜、春菊、ホウレンソウ、カブなど葉もの野菜を栽培する予定。